いよいよ清明
-----春の訪れを味わう
二十四節気のひとつ「清明」は、万物が生き生きと芽吹き、空気が清らかで明るく澄んだ季節を指します。穏やかな陽光が降り注ぎ、野山は鮮やかな緑や色とりどりの花々で彩られます。この季節は、古来より日本人が四季折々の自然に感謝しながら、家族や地域とともに心豊かに過ごしてきた特別な時期でもあります。春を感じる暮らしを、旬の食材を楽しみながらご家族で味わってみませんか。
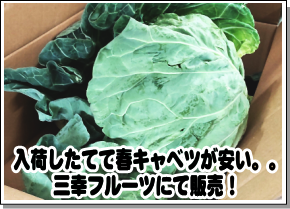
清明の食卓を彩る旬の食材。
春の食卓を豊かにする旬の食材をいくつかご紹介します。
- 菜の花:鮮やかな黄色と緑が特徴の春を代表する野菜で、ビタミンやミネラルが豊富です。
- たけのこ:春の訪れを告げる代表的な食材。食物繊維が豊富で、シャキシャキとした食感が魅力です。
- ふき:独特のほろ苦さがあり、春の味覚として親しまれています。薬効もあり、胃腸を整える効果があります。
- 新じゃがいも:皮が薄く柔らかく、甘みが強いのが特徴。ビタミンCも豊富です。
- わらび:春を感じさせる山菜で、クセのない味わいと柔らかな食感が楽しめます。
- アスパラガス:瑞々しく甘みがあり、栄養価も高い春野菜。疲労回復や抗酸化作用があります。
- グリーンピース:鮮やかな緑色が美しく、豆特有の甘さが魅力。タンパク質や食物繊維を多く含みます。
- 春キャベツ:柔らかくて甘みが強く、サラダなど生食にも適しています。ビタミンUが豊富で胃腸に優しい野菜です。
清明の食卓に欠かせない旬の食材。
日本では昔から、春を感じさせる代表的な食材として「菜の花」と「たけのこ」が親しまれてきました。菜の花は江戸時代にはすでに庶民の食卓に上り、雛祭りの料理や春の行楽弁当を彩る食材として愛されてきました。鮮やかな黄色と緑の美しい色合いは、見た目の華やかさだけでなく、栄養価も豊富で、現代の健康志向の若い世帯にも人気です。一方、たけのこは古くは平安時代から宮廷料理に使われ、春の贅沢な味覚として高貴な人々にも愛されていました。また、農村地域では春になると家族や地域の人々が集まり、たけのこ掘りを楽しむ風習も根付いており、地域の交流の機会としても大切にされています。旬の食材を味わうことは、季節を楽しむだけでなく、日本人が育んできた豊かな食文化を継承することにも繋がっています。
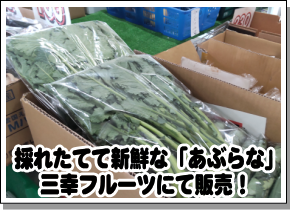
今回は、この中から特に春らしさを感じられる「たけのこ」と「菜の花」を使った料理をご紹介します。菜の花とたけのこのごはんで、春らしい香りと食感を楽しんでみましょう。
【材料(2~3人分)】
- 米:2合
- 菜の花:1束
- 茹でたけのこ:150g
- 油揚げ:1枚
- だし汁:400ml
- 醤油:大さじ2
- 酒:大さじ1
【作り方】
- 米を研いでざるに上げ、しっかり水気を切る。
- 菜の花はさっと茹で、冷水にさらして水気を絞り、食べやすい長さに切る。
- たけのこを薄切りにし、油揚げは熱湯で油抜きし細切りにする。
- 炊飯器に米、たけのこ、油揚げ、醤油、酒、だし汁を入れて炊く。
- 炊きあがったら菜の花を加えて軽く混ぜ、しばらく蒸らして完成。

食材調達は桐生市場で。
新鮮な旬の食材を手に入れるなら、桐生市場がおすすめです。桐生市場には地元産の採れたての菜の花や丁寧に処理されたたけのこが豊富に並びます。市場の活気ある雰囲気や生産者との触れ合いは、日常の買い物にはない楽しさがあります。市場を訪れることで、生産者の方から直接食材の選び方や美味しい食べ方のコツを教えてもらえるかもしれません。家族みんなで市場に出かけて、季節を感じるお買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか。
清明をめぐる歴史と生活習俗。
清明は古くから農作業を本格的に始める節目とされ、田畑の準備や家の大掃除を行い、新しい季節を清々しく迎える習慣がありました。特に昔は、この時期に農具を清めたり、種まきや苗作りなど一年の農作業の準備をする重要な節目とされていました。また、清明の頃にはご先祖様のお墓参りを行い、先祖への感謝と敬意を表す習慣もありました。
また、清明の頃には地域によってさまざまな花見や山菜採りなどの行事が行われます。満開の桜を楽しむお花見はこの季節の代表的な行事であり、家族や友人、地域の人々が集い、交流を深める大切な機会となっています。また、山菜採りなどの自然に触れ合う活動を通じて、地域の人々が互いに助け合い、協力することも、この季節ならではの習慣です。
現代でも、この季節には自然を楽しむキャンプやトレッキングなどのレジャーも盛んに行われます。家族や友人と共に旬の食材を味わいながら、春の息吹を感じることは、心身ともに健康的で豊かな暮らしを実感できる機会です。
今年の清明は、桐生市場で季節の恵みを揃え、手作りの美味しさを家族みんなで味わいながら、春ならではの素敵な時間をお過ごしになられてはいかがでしょうか?
